
毎日の歯磨きについて🪥
皆さんは歯ブラシ以外に使っているものはありますか? 歯ブラシだけでの清掃効果は60%と言われています。フロスや歯間ブラシ、マウスウォッシュなどの補助用具を使うことで清掃効果をあげることができます。 歯ブラシ以外のも […]

皆さんは歯ブラシ以外に使っているものはありますか? 歯ブラシだけでの清掃効果は60%と言われています。フロスや歯間ブラシ、マウスウォッシュなどの補助用具を使うことで清掃効果をあげることができます。 歯ブラシ以外のも […]

こんにちは☀ 受付・アシスタントの大木です。 暑くなってきましたがいかがお過ごしでしょうか? 今回は、歯に良い食べ物を紹介しようと思います🦷 ○乳製品、海藻類:これらにはカルシウムが豊富に含まれており、歯を丈夫に強くして […]

出っ歯は歯列矯正でこんなに綺麗になります! 口元の印象を大きく左右する出っ歯。 コンプレックスに感じている方も多いのではないでしょうか。 そんなお悩みを解消する手段として、注目されているのが歯列矯正です。 この記事では、 […]

歯医者に初めてかかるとき、「初診料はいくらかかるの?」「どんな費用が含まれているの?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。 こちらのページでは、歯科医院で初診料が発生する条件や症状ごとの費用目安、レントゲンや検査な […]

歯列矯正は見た目の美しさだけでなく、噛み合わせや発音といった機能面の改善にもつながる大切な治療です。 しかし、治療方法や症状によって費用は大きく異なるため不安を感じる方も多いでしょう。 この記事では、症状や治療法、年齢別 […]

みなさんこんにちは! 虫歯や歯周病など何らかの理由で歯が抜けてしまったり残せずに抜歯したあと、奥歯で目立たないからと言って歯がないままで生活している方も多いのはないでしょうか。 しかし、歯というのは一本ないだけでもお口の […]

エス歯科はサッカーJ1リーグ「横浜FC」のオフィシャルクラブデンティストを務めており、年に一度、スポンサーマッチが行われます。 今年は5/10開催のアビスパ福岡戦。当日はスタッフ全員で応援に行きました! & […]

2025年5月10日、ニッパツ三ツ沢球技場で横浜FCのマッチデープログラム「エス歯科マッチ」が開催されます! 横浜FCはエス歯科グループがオフィシャルクラブデンティストとしてお口のケアのサポートをしているサッカーJ1リー […]

2025年4月1日、エス歯科グループの入社式を執り行いました。 新入社員の皆様、入社おめでとうございます! 今年度は歯科医師4名、歯科衛生士20名、受付・歯科助手10名の計34名を迎え入れることができました。   […]
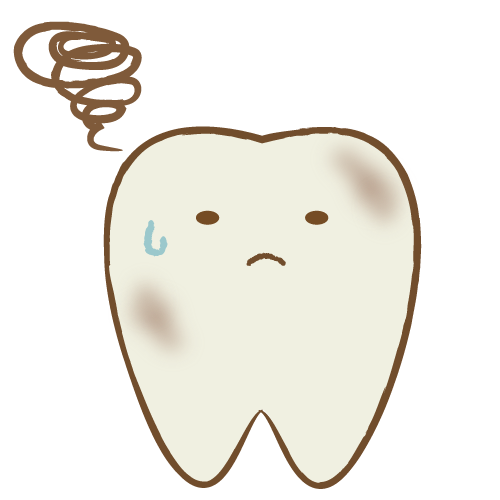
~歯の色について〜なぜ色が変わるのか〜 歯の色の変化は大きく分けて 1 歯の表面への着色 2歯の内部の色の変化 の2通りがあります。 まず、歯の表面への着色は、飲食物やタバコによるものです。 飲食物ではカレーやコーヒー、 […]
〒194-0013
東京都町田市
原町田6-2-6
町田モディ6F
町田駅より徒歩1分
【提携駐車場について】
・いちのや駐車場
・ぽっぽ町田パーキング
お会計2千円以上で1時間までのサービス券をお渡しいたします。
自費治療1万円以上お支払いの方は、治療完了までの駐車場代金のサービス券をお渡しいたします。
現金/クレジットカード/PayPay
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00〜13:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ■ | ✕ |
| 14:30〜19:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ■ | ✕ |
042-812-2555

WEB予約

LINE予約
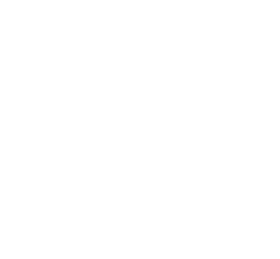
お電話
